柊
Spot-nape ponyfish
スズキ目 スズキ亜目 ヒイラギ科 ヒイラギ属
・・・
本州の沿岸の波の穏やかな砂底地に生息する小型魚。
成長しても全長15cmほどで、キラキラと銀色に輝く魚体をしています。

ヒイラギ科の魚は日本に7属14種います。
ヒイラギ科の代表となる本種は、項部と背びれの前方に黒い斑模様があるのが特徴です。
・・・
和名の由来は体型が植物のヒイラギの葉に似ているため。
ひれが尖っていて触るとチクチクする点も、ヒイラギの葉によく似ています。
ヒイラギは「鳴く魚」として知られており、釣り上げたときにギーギーと音を立てることがあります。
これは体内の前上顎骨と額骨を擦り合わせて出す音です。
・・・
ヒイラギの銀色の体色はタチウオと同じ「グアニン結晶板」によるものです。体に光を反射させることで、水面から差し込む太陽の光に紛れ込むことができます。
そのため体の前部には鱗がありませんが、代わりに粘液で全身を覆うことで体を外傷から守っています。
さらにヒイラギは光を反射させるだけでなく、体内の食道付近に発光器を備えています。
この発光は共生するバクテリアによるもので、腹部を光らせることにより、下から見上げると水面からの光と同化して体のシルエットを隠すことができると考えられています。
総じて、体を光らせることで外敵から身を守るよう進化してきた種と言えます。
・・・
ヒイラギの口吻は前下方向にニュッと伸ばすのとができます。
この口を使って、水底に潜む小動物を吸い込むようにして補食します。
このように海底のエサを探す習性があるため、キス釣りやハゼ釣りなどの底を引いてくるような餌釣りの際に、外道として姿を表すことが多々あります。
食味はさっぱりとして悪くないようですが、可食部が少ないことや粘液でヌルヌルしていることから、釣り人からはあまり喜ばれません。
釣り方
ちょい投げ釣り等で釣れることがあります。底質は砂や砂泥になった海域を狙いましょう。
キスやハゼと生息域を同じくする場合が多いようです。
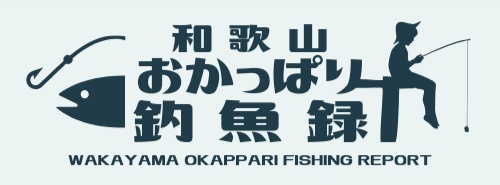



コメント